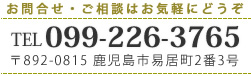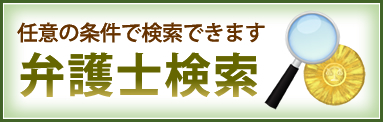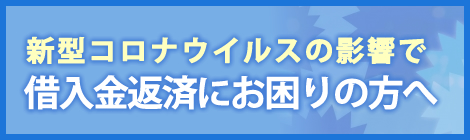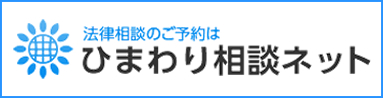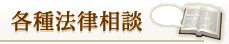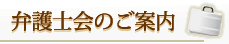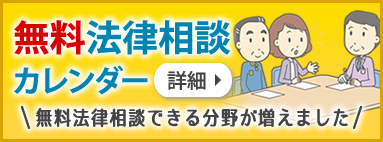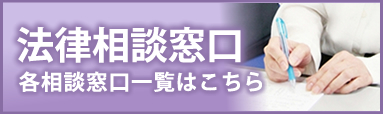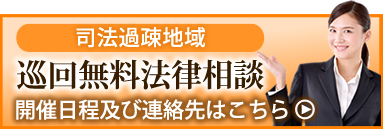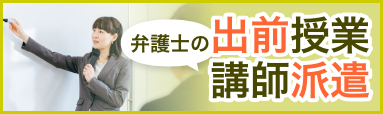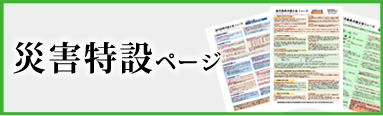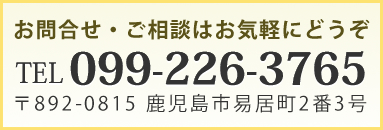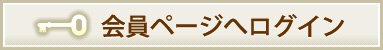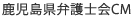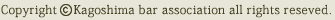勧告書・警告書
再審手続のための弁護人依頼書発送許可に関する勧告書(刑務所長あて)
鹿児島刑務所長 山内博文 殿
令和7年2月19日
鹿児島県弁護士会
会 長 山 口 政 幸
同拘禁問題対策委員会
委員長 本 多 剛
勧告書
当会は、申立人A(以下「申立人」と言います。)からの人権救済申立事件について、当会拘禁問題対策委員会に付託して調査した結果、当会常議員会の議を経た上、鹿児島刑務所に対し、以下のとおり勧告します。
第1 勧告の趣旨
申立人は、閉居罰の執行中であった令和5年9月27日、前刑についての再審手続のための弁護人選任及び再審書類作成のために必要であるとして、福岡県弁護士会宛に弁護士を紹介してもらうための手紙を発送すべく、受罰中認書許可願を提出したが、貴所は拒絶した。しかし、収容者が再審請求のために弁護人を紹介してもらうべく弁護士会に手紙を発送しようとする場合に、受罰中であることを理由としてこれを不許可にすることは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第152条第1項第6号の運用を誤ったものであり、受刑者の信書発受の自由を不当に制限する措置であるとともに、刑事訴訟法第440条第1項の再審請求における弁護人選任権も侵害するものである。よって、今後、被収容者から各弁護士会に対して再審請求のための弁護人依頼文書の発送の申請があった場合には、閉居罰受罰中であっても、速やかにその発送を許可するよう勧告する。
第2 勧告の理由
1 申立ての趣旨
申立人は、令和5年9月、再審請求の手続のために弁護人を選任したいと考え、福岡県内の弁護士を紹介してもらうべく、福岡県弁護士会に文書を発送しようとしたところ、閉居罰中であることを理由に当該文書を出すことを鹿児島刑務所から許可されなかった。
そのため、申立人は、閉居罰中に福岡県弁護士会宛に再審請求の弁護人の紹介を求める文書の発送が許されなかったことが違法であるとして、当会に本件人権救済を申し立てた。
2 調査の経過
令和6年2月 当会拘禁問題対策委員会から鹿児島刑務所に対して照会
令和6年3月 鹿児島刑務所から回答
令和6年6月 同委員会から鹿児島刑務所に対して再照会
令和6年9月 鹿児島刑務所から回答
3 照会に対する回答等から認定した事実
(1)鹿児島刑務所は、申立人に対し、令和5年7月27日から同年8月5日までの間、同年9月26日から同年10月15日までの間、及び同年11月7日から12月6日までの間、閉居罰を科していた。
(2)申立人は、閉居罰中であった令和5年9月27日、鹿児島刑務所に対し、「受罰中認書許可願」と題する願箋(以下「本件願箋」という。)を提出した。鹿児島刑務所からの回答によれば、本件願箋には、「再審準備中につき現在弁護人の選定もしておらず意見書を弁護人と作成しなければならず期間が40日しかなく罰終了後では間に合わないので受罰中認書許可願います。弁護人と意見書に対する内容のやりとりと選任の為。福岡県弁護士会」と記載されるとともに、福岡県弁護士会の住所が記載されていた。申立人は、福岡での再審手続のため、弁護士を紹介してもらうべく、福岡県弁護士会に文書を発送しようと考えていた。
(3)鹿児島刑務所は、令和5年9月29日、申立人に対し、本件願箋に係る出願を取り計らわない旨告知した。
(4)鹿児島刑務所は、受罰中の受刑者から弁護士会宛の文書を発送したい旨の許可の申出(「受罰中認書許可願」)があった場合、一般的にどのように対応しているか(どのような判断基準で許可の可否を決めているか等)との照会に対し、「関係法令により閉居罰執行中に原則停止となる信書の発信については、発信の必要性及び緊急性を総合的に考慮し、相当と認められるかを判断しているところ、当該被収容者が信書を作成していない場合には提出された願箋(発信の願い出)の内容により、既に信書を作成している場合には当該信書の内容により検討し、その結果、期限の切迫や閉居罰執行終了後の発信では当該被収容者に不利益が生ずるなどの理由があるときは、発信を認める一方、願箋に記載された内容だけでは判断が困難な場合は、願箋の記載内容のみで判断することはなく、当該被収容者に願箋の記載内容の確認を行い、より理由が明らかになるような記載や理由等を疎明できる資料があれば提示等するよう指導していますが、当該指導に応じ、理由等が確認できた場合は、その理由等を踏まえ、改めて発信の許否を判断し、当該指導に応じず、先に提出した願箋内容以外に理由等が確認できなかった場合は、当該被収容者に指導した後の状況やこれまでに提出された願箋の内容を踏まえて判断し、緊急性及び必要性が認められなければ、発信を許さないとしています。」と回答した。
(5)また、鹿児島刑務所は、本件願箋を取り計らわなかった理由について、以下のとおり回答した。
・「当所は、(書面作成の期間を)40日間とする内容の疎明資料の提出を指示したところ、申立人は「ありません。」と述べた。さらに、当所は、同願箋の緊急性及び必要性について詳しく記載するよう指示するも、申立人は翻意せずに同願箋を提出したことから、当所は同出願を取り計らわないこととしたもの」
・「申立人の出願した本件発信については、願箋の内容から緊急性は認められなかったことから、閉居罰執行中に発信を認める必要性はないと判断したものです。なお、本件発信の出願について、申立人が、閉居罰執行終了後に再度発信を願い出たことから、発信を認める対応をしています。」
4 判断
(1)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下、単に「法」という。)第152条第1項は、閉居罰中の受刑者について停止対象行為を列挙している。同第6号には、「六 信書を発受すること(弁護人等との間で信書を発受する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。」との規定がなされており、閉居罰中であっても、「訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合」には、信書の発受が認められる。
(2)本件は、再審請求のために弁護人を選任すべく、弁護士を紹介してもらうために弁護士会に手紙を発送しようとした事案である。
刑事訴訟法第435条によれば、再審請求とは、一定の事由がある場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、行うことができる訴訟行為である。そして、刑事訴訟法第440条第1項は「検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる」としている。
また、弁護士会とは地方裁判所の管轄区域ごとに設立されており(弁護士法第32条)、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とした法人である(弁護士法第31条)。
(3)現在、再審請求手続について国選弁護の制度は存在せず、刑事訴訟法第440条第1項の弁護人選任権は認められていても、弁護人となる弁護士は再審請求を行う者が自分で探して、依頼しなければならないのが実情である。そして、地方裁判所の管轄区域ごとに設立された弁護士会は、当該管轄区域内で活動する弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とした法人であるから、当該区域で活動する弁護士を把握している。そうすると、弁護士紹介制度の有無や紹介の当否は各地の実情や依頼内容によるとしても、再審請求手続のために弁護士を紹介してもらおうと弁護士会に相談することは、再審請求の弁護人選任を考えている者にとって、再審請求弁護人の選任に向けた行動の第1歩と言える。
(4)また、再審事由があると被収容者が考えている場合(とりわけ、冤罪事件と考えているような場合)においては、当該被収容者は受刑自体に納得がいかず、その結果、遵守事項に従わなかったり、刑事施設の職員の指示に従わなかったりして懲罰を受ける(法第150条第1項)ことがあり得、閉居罰になることもあると考えられる。
再審事由があると考えて受刑に納得がいかない被収容者にとって、再審請求を求める権利及び再審請求の弁護人選任権は極めて重要な権利であり、むしろ受刑に納得がいかず閉居罰を受けている被収容者にとってこそ自己の置かれた状況を救済するために必要な手段である。
(5)それにもかかわらず、閉居罰中である被収容者が、再審請求のため、再審請求弁護人の選任に向けた行動の第1歩である弁護士会宛の文書を発送するという手段を制限されることは、閉居罰を科されている間は再審請求弁護人の選任はおろか、その準備すらできないことを意味し、その権利侵害の程度は著しく、許されないものと言わざるを得ない。
(6)そこで本件についてみるに、申立人は前刑についての再審請求のために弁護人選任をしようと考え、弁護士を紹介してもらおうと福岡県弁護士会宛に文書を発送することを願い出たのであるから、発送を予定していた文書は権利の保護に必要と認められる場合に該当する信書であり、法第152条第1項第6項かっこ書きの「訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合」に該当すると言える。
この点、鹿児島刑務所は、「関係法令により閉居罰執行中に原則停止となる信書の発信については、発信の必要性及び緊急性を総合的に考慮し、相当と認められるかを判断して」おり、「申立人の出願した本件発信については、願箋の内容から緊急性は認められなかったことから、閉居罰執行中に発信を認める必要性はないと判断した」という。
本件願箋には、「再審準備中につき現在弁護人の選定もしておらず意見書を弁護人と作成しなければならず期間が40日しかなく罰終了後では間に合わない」旨記載されており、鹿児島刑務所が「40日」という期間制限の疎明を求めていたことに照らして、鹿児島刑務所の言う「緊急性は認められなかった」とはこの「40日」のことを指すものと解される。
「40日」という期間制限の内実がいかなるものであったかは明らかではないものの、法第152条第1項第6号は「権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合」としか規定しておらず、緊急性は法の規定していない加重要件であり、認められない。また、「40日」という期間制限の内実が明らかにならない限り、「権利の保護に必要と認められる場合」に当たらないと鹿児島刑務所が判断したと解釈しても、①本件願箋の記載内容に照らせば、申立人が再審請求の弁護人を選任するため、福岡県弁護士会に弁護士を紹介してもらおうとしていたこと、②宛先は私人ではなく、弁護士法で定められた弁護士会であったこと、③再審請求を求める権利及び再審請求の弁護人選任権は刑事訴訟法で認められている基本的かつ重要な権利であることに照らせば、「40日」という期間制限の内実が明らかでなくても、本件願箋で求められている文書が、閉居罰中の申立人にとって法第152条第1項第6号かっこ書きの「権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合」に該当しないと言うことはできない。
したがって、鹿児島刑務所が、令和5年9月29日、申立人に対し、本件願箋に係る出願を却下したことは、法第152条第1項第6号の運用を誤ったものであり、受刑者の信書発受の自由を不当に制限する措置であるとともに、刑事訴訟法第440条第1項の再審請求における弁護人選任権も侵害するものである。
(7)当会としては、被収容者から各弁護士会に対して再審請求のための弁護人依頼文書の発送の申請があった場合には、受罰中であっても、信書の発受が許可されなければならないと考える。よって、上記勧告の趣旨記載のとおり勧告する。
以上